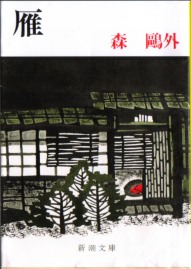文学と雁 ガンについてのエトセトラ
小説では
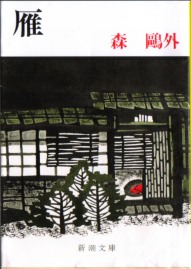 |
「雁(がん)」 森鴎外作
1912年の作品で 明治の文豪森鴎外の代表作の一つ。
高利貸しの妾となった女が家の近所を通る学生に思いを募らせ自我に目覚める。学生への思いを実らせようとするが偶然の重なりで遂げられない。
雁は学生が当てる気がなく投げた石に当たって死んでしまうという場面に登場。偶然の挫折の象徴的として使われる。
明治13年という設定で書かれ、このころは東京上野の不忍池に雁がいたこと、雁鍋を好んで食べたが、雁を大ぴらに持ち運ぶことははばかれたことなどがわかる。
|
 |
「雁(がん)の寺」 水上勉作
1961年に文藝春秋に連作。この作品で直木賞を受賞した。
舞台は昭和8年の京都の禅寺。寺には檀家で京都の日本画壇の重鎮によって描かれた傑作の雁の水墨画が描かれている。画家が死にその妾だった女が寺の住職の世話になる。寺には若狭からやってきた父なし子の小僧がいる。住職と女の愛欲を盗み見た小僧は住職を殺そうとする。
小僧が去った後寺の雁の絵は母雁が子雁にえさを与える部分がむしりとられていた。
水上には「旅雁の記」「雁の死」「帰山の雁」「雁帰る」など雁をタイトルにした作品が多い。 |
|
|
歳時記では
和歌の世界では花鳥風月の美意識に基づき秋を代表する鳥とされてきた。万葉集をはじめ各和歌集に
「秋の田の穂田を雁がね暗けくに夜のほどろにも鳴き渡るかも」(聖武天皇=万葉集)
「待つ人のあらぬものから初雁のけさ鳴く声のめずらしきかな」(在原元方=古今集)
「横雲の風にわかるるしののめに山とびこゆる初雁の声」(西行=新古今) などさまざまな歌がある。
短歌では(かり)と呼ばれることが多いのに対し俳句では(がん)と読むことが多い。秋の季語だ。
「病雁の夜空に落ちて旅寝かな」(芭蕉)
「雁がねの竿になるときなほさびし」(去来)
「紀の路にも下りず夜を行く雁ひとつ」(蕪村)
など秋の寂しげな句が多い。
明治以後も
「雁鳴いてさみしくなりぬ隠れんぼ」(篠田悌二郎)
「雁渡る菓子と煙草を買ひに出て」(中村草田男)
「最上川ながるるうへにつらなめて雁飛ぶころとなりにけるかも」(斎藤茂吉)
全体的に夕方や夜の雁をうたった作が目立つ。
初雁、雁渡る、来る雁、雁の棹、雁行、雁字、雁陣、落雁、雁鳴く、雁の声、真雁、菱喰い、白雁、黒雁、酒顔雁なども秋の季語
春に北へ帰るときの姿を現す「帰雁」は春の季語。分かれの意味もありやはり寂しげな句が多い。
「帰る雁門田も遠くおもはるる」(蕪村)
「胸の上に雁行きし空残りけり」(石田波郷)
帰る雁、雁帰る、行く雁、去ぬ雁、名残の雁なども春の季語
津軽では雁が渡来するとき木片を持って渡り時々海に浮かべて休み、海岸に着いたとき木片を置き、北へ帰るときそれを再び持って帰るという言い伝えがある。春海岸に残った木片は秋、冬に亡くなった雁のものでその供養のため木片を集めて風呂を焚くという。ここから「雁風呂」という季語が生まれた。
「雁風呂や海あるる日は焚かぬなり」(高浜虚子)
「雁風呂や日の暮れ方を波さわぐ」(豊長みのる)
古典では
雁は「常世の国」や「冥界」など異境から使いという考え方もあった。後拾遺集に出てくる赤染衛門の歌は
「久しくわずらひけるころ、雁のなきけるを聞きてよめる」という詞書に続いて
「おきもゐぬ我がとこよこそ悲しけれ春かへりにし雁もなくなり」
源氏物語にも京を思う歌の中に雁がでてくる。
さらに光源氏の長男、夕霧の妻の名は「雲居の雁」。
清少納言の枕草子にも雁は出てくる。
まず冒頭の第1段、「春は曙…」「夏は夜…」に続き
「秋は夕暮…」の文で、烏に続いて「まいて雁などのつらねたるが、いとちひさく見ゆる、いとをかし」と書いた
さらに38段「鳥は」の章で「雁の聲は遠く聞えたるあはれなり」としるした。
雁の飛ぶ姿も声も平安人には印象深かったのだろう。


エトセトラ目次
雁行記