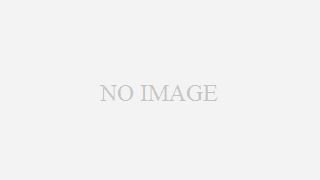 二十四節気
二十四節気 霜降、20度を超える暖かい日だった
二十四節気・霜降(そうこう)
露が冷気で霜となって降りてくる頃。
前の二十四節気は寒露で、言葉からも寒さが増してくることが伝わる。
いよいよ秋が深まってくる。平地でも木々の紅葉が始まるでもある。
2018年は...
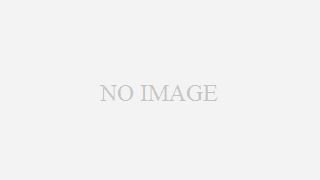 二十四節気
二十四節気 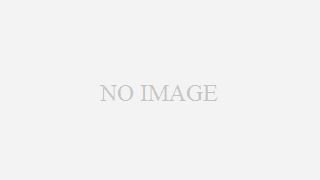 二十四節気
二十四節気 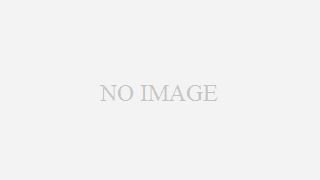 二十四節気
二十四節気 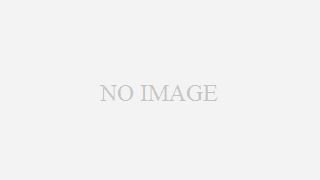 二十四節気
二十四節気 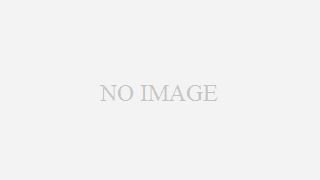 二十四節気
二十四節気 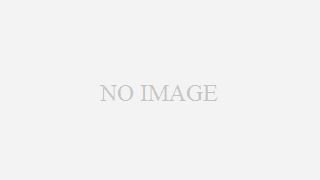 二十四節気
二十四節気 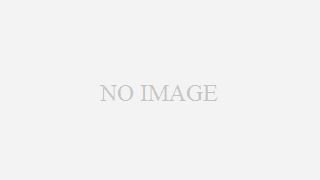 二十四節気
二十四節気 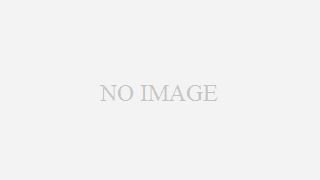 二十四節気
二十四節気 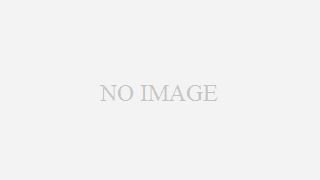 二十四節気
二十四節気 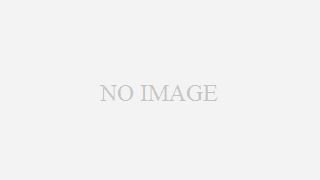 二十四節気
二十四節気